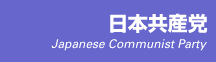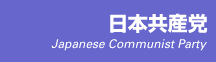|
2006年3月22日(水)
文教科学委員会
「教科書の特殊指定」「医師不足」について
- 公正取引委員会の教科書の特殊指定廃止方針に対し、宣伝や営業に経費をかけられる大手発行者による教科書の寡占化がすすむことを指摘。京都府北部地域や静岡県伊豆地域などで産婦人科・小児科などの廃止や病棟休止で住民に不安が広がっていることを指摘し、入学定員削減政策の見直しや地域医療の担い手の育成となる医療教育の改善を要求。
|
- 井上哲士君
日本共産党の井上哲士です。
まず最初に、公正取引委員会に教科書の特殊指定廃止問題でお聞きをいたします。
先日、この問題での意見募集を行うことが発表されまして、教育関係者から大変不安の声が上がっております。なぜ教科書の特殊指定廃止の意見募集に至ったのか、御説明をいただきたいと思います。
- 政府参考人(舟橋和幸君)
御説明申し上げます。
私ども公正取引委員会におきましては、昨年の秋から、いわゆる特殊指定、これは特定の事業分野において不公正な取引方法とは何かということをそれぞれの事業分野ごとに定めておる、そういうものでございますけれども、当時の時点で七つございました。
そのうちの、ここ一、二年で制定された二つを除いた五つについて見直しを行うということで五か月ぐらいがたったわけでございますけれども、見直しの観点としましては、制定されたときの事情が今もあるかどうか、制定理由があるかどうか、そして、それから二番目に、特殊指定とは別に一般指定というのがございまして、一般指定で対応ができないかどうか、仮に特殊指定で対応すべきという場合でも、今の特殊指定が過剰規制になっているかどうか、そういった観点から見直しを行ってきておるところでございまして、七つのうち二本を除いた五本あったわけでございますけれども、うち一本はもう既に廃止をいたしました。それから、一本は検討中でございます。それから、三本につきましては、先生今御指摘がございましたとおり、パブリックコメントに付しておるというところでございまして、このうち教科書の特殊指定、これは現在パブリックコメント中でございますけれども、今から五十年前の昭和三十一年に制定されたものでございまして、背景としては、昭和二十四年に国定教科書から検定教科書に移行したということに伴って、教科書の採択関係者に対する金品等の提供行為が横行、激化したと、そういった背景を踏まえて今から五十年前に制定されて、そのまま今も来ておりますけれども。
その後、五十年が経過いたしまして、この五十年という期間の間に、地区ごとにまちまちであったそういう採択の体制というものも、昭和三十八年の教科書無償化などを契機に整備されてきておると。それから、最近では、教科書の採択に関する国民の関心の高まりも踏まえ、手続の透明化も図られてきておるということがございますし、さらに、近年では公務員の倫理に対する規制、これも一段と強化をされてきておるということがございます。
こういった中で、特殊指定が禁止をしております教科書採択関係者への利益供与、それから他の教科書に対する誹謗中傷、そういったことによって教科書の採択がゆがめられるおそれというものは五十年前のこの特殊指定制定当時と比べて著しく減少をしてきているんじゃないかと、こういうことでございまして、教科書の分野に特殊指定を設けて特別に規制を行う必要性はなくなってきているんではないかという考えで、三月十六日、先般、規制簡素化の観点から、廃止についての意見募集を行ったところでございます。
今後、これ四月十七日が締切りになっておりますので、寄せられた御意見等を踏まえて、この特殊指定の取扱いについては適切に判断をしてまいりたい、そういうふうに考えております。
- 井上哲士君
特殊指定を外しますと、宣伝や営業活動に大きな費用を掛けることができる大手発行社が一層有利になって教科書の寡占化を招くんじゃないかという不安の声が寄せられております。
この特殊指定の制度が公正な教科書採択に果たしてきた役割について、文部科学省としてはどういうお考えでしょうか。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
独占禁止法に基づきます特殊指定の果たしてきた役割についてのお尋ねでございますが、私ども具体的には大きく二点あろうかと思っております。
一つは、教科書発行者が自らの採択を有利に導くために採択関係者に対して物品の提供などの利益供与を行ういわゆる取引誘因行為、これが禁じられるわけでございます。それからもう一つは、他の教科書発行者や教科書に対して中傷誹謗等の妨害を行うようないわゆる取引妨害行為、こういった行為も不公正な取引方法として指定をされるわけでございます。
こういった行為が明確に不公正な取引方法としてこの告示を受けまして禁止をされるということで、文部科学省としても、毎年、採択の公正確保に向けて教科書発行者に対して通知を発出し、独占禁止法に基づく規制を遵守するよう指導してきたところでございまして、その意味で、教科書採択の公正確保を図る上でこうした規制は重要な役割を果たしてきたと認識をしているところでございます。
- 井上哲士君
現状でも、見本本をすべての教育委員会に五冊ずつ送るのも非常に負担がありまして、経済的理由から送付できずに採択対象から外される発行者も少なからずあるわけですね。そういう点でも非常に大きな役割を果たしてきたと思うんですが、今後、公正な教科書採択を維持をしていく上で、その対応について大臣から御見解を伺いたいと思います。
- 国務大臣(小坂憲次君)
今、特殊指定についていろいろ述べていただきましたが、仮に現時点で特殊指定が廃止された場合、これまで長年にわたりまして運用され、またその中で蓄積してまいりました運用に関する細部の考え方等もあるわけでございまして、規制が急に廃止されたことによりまして採択の関係者の間に混乱を招かないか、そういうことが若干懸念をされておるわけでございます。
現在、公正取引委員会において特殊指定の廃止に関する意見募集を行っているところと承知しておりまして、公正取引委員会における手続を注目をしながら、引き続き、教科書採択の公正確保が図られるようによく検討してまいりたいと考えております。
- 井上哲士君
公正取引委員会には、廃止を前提にした意見募集ではなくて、広く関係者の意見も聞くし、募集期間も大幅に延ばして、性急な決定がないように、無用な混乱を招かないように強く求めておきます。
次に、医師不足と医学部定員、教育についてお聞きをいたします。
今、医師不足の問題が非常に深刻でありまして、私の住まいする例えば京都府の北部地域、京丹後市の市立弥栄病院の産婦人科、それから舞鶴市の独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センターの産科診療が廃止をされまして、安心してお産ができない地域になろうとしております。先日、静岡の伊豆の地域のお話も伺いましたけれども、例えば東伊豆町、診療機関や科目がなくなって、産婦人科、小児科、泌尿器科、脳外科などは地域外に行かなくちゃいけない、二次救急は一時間も掛けて搬送する。それから、富士川町の共立蒲原総合病院、これは医師が八人も一遍に減りまして、三月から内科、小児科、それから時間外・救急医療、この縮小、そして一部病棟の休止ということが出ておりまして、非常に地域住民から不安の声が上がっております。
まず厚生労働省にお聞きしますけれども、こういう医師不足の実態をどのように把握をして対策を考えていらっしゃるんでしょうか。
- 政府参考人(中垣英明君)
ただいま委員御指摘の医師の不足あるいはその偏在の問題につきましては、へき地等の特定の地域でありますとか、それから、今も御指摘もございましたが、産科、小児科等の特定の診療科において偏在による医師の不足感が非常に強く、その確保に困難を伴ってきておるということで認識しております。
このような問題に対応するため、私どもといたしましては、文部省及び総務省とともに関係省庁連絡会議を開催いたしまして、昨年八月には医師確保総合対策を取りまとめるなど各般の取組を進めてきております。中でも早急な対応が求められております小児科医及び産科医の確保につきましては、昨年末に各都道府県に対しまして、公立病院を中心に、小児医療、産科医療の機能を集約化、重点化するための検討を十八年度末までに行うようお願いしたところでございます。
また、今国会に医療制度改革の一環として提出しております医療法等の改正法案におきましては、救急医療、へき地医療、小児医療、周産期医療等の従事者の確保を推進するために医療対策協議会というものを制度化するということで、法制度面からも必要な措置を講ずることといたしております。
このほか、平成十八年度予算及び十八年度の診療報酬改定においても必要な措置を講じてきておりまして、こうした取組を通じまして引き続き総合的な医師確保対策に取り組んでまいりたいと考えております。
- 井上哲士君
医療改革法案が果たして医療の確保に役立つのかどうかは、これはまた別のところで議論をしたいと思いますが、新しい研修制度の影響もあって、特に地域医療を支えてきた自治体病院が大変医師不足が深刻になっております。
全国自治体病院開設者協議会などの三者が、文部科学、厚生労働、そして総務省、三つの大臣あてに医師不足・偏在の是正に関する要望を出しておりますけれども、その緊急要望のトップは医師数の確保であり、そのための大学入学定員削減方針の見直しということになっておりますけれども、この入学定員の問題、大臣の御見解を伺いたいと思います。
- 国務大臣(小坂憲次君)
御指摘のように、地域における医師不足、とりわけ診療科の偏在というような問題が大きく指摘をされておりまして、私どもも、ただいま御指摘のように、厚生労働省、文部科学省、総務省の三省で検討を進めておるわけでございますが、現在、厚生労働省におきまして医師需要の見通しの見直しについて先ほどのお話のように検討をされております。医学部の入学定員の在り方については、その検討結果を十分に踏まえることが必要だと考えております。
そもそもの昭和五十七年の閣議決定の合理的な養成計画を踏まえ、六十一年に一〇%削減という基本的な方針が策定をされ、そして現在はまだその一〇%の目標達成の道半ばでございます。しかしながら、一方で委員今御指摘のような事情が出ておりますので、文部科学省におきましては、この見直しの結果及び医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議の調査研究を踏まえながら、今後、医学部の入学定員の在り方についての検討を行ってまいりたいと存じます。
- 井上哲士君
今もありましたように、厚生労働省が一九八六年に将来の医師需給に関する検討委員会を発足さして医学部定員の削減というものが打ち出されましたし、その後の閣議決定も行われてまいりました。
しかし、国際的に見ますと、例えば、OECDに加盟している二十九か国のうち、人口比の医師数というのは日本は二十六番目で、下から四番目ということになっております。そして、今、日本よりもむしろ医師数が多いOECDの先進国は、むしろ医師を増加させるという傾向にあります。そういう中で日本は逆行しているわけでありますけれども、厚生労働省は現時点においても医師が過剰になってきていると、こういう認識でおられるんでしょうか。
- 政府参考人(中垣英明君)
医師数につきましては、近年、大体毎年三千五百名から四千名程度、順調に増加してきておるところでございます。
私ども、平成十年に取りまとめられました医師の需給に関する検討会報告によりますれば、遅くとも平成二十九年ごろからはもう供給医師数が必要医師数を上回って、将来的に供給過剰になるという報告を受けておるところでございます。
その一方、今委員からも御指摘ございましたような医師の偏在の問題等もございますので、私ども、今、医師の需給につきまして、女性医師の増加とか、そういった医師の需給を取り巻く状況とか、そういった先ほど来ございました地域、診療科における偏在等を総合的に勘案した需給見通しを行うために、平成十七年二月から医師の需給に関する検討会を新たに開催いたしまして、その場で検討を行っておりまして、現在最終報告書の取りまとめに向けて検討を行っておるというところであります。
- 井上哲士君
過去の閣議決定自身が医療の必要性というよりも医療費の抑制という観点からなされた側面が強くて、それ自体が私は妥当でなかったと思うんですが、今もありましたように、その後、医療と医師をめぐる環境は非常に大きく変化をしております。その点からも見直しが必要だと思うんですけれども、その定員削減が打ち出された一九八六年と現在と、医学部の学生数、その中で女性の占める割合はどうなっているでしょうか。
- 政府参考人(石川明君)
医学部の入学者における女子学生の割合についてお尋ねがございました。
一九八六年、昭和六十一年度におきましては、入学者八千二百八十三人中千六百八十一人、割合にいたしまして二〇・三%が女子学生でございました。直近の二〇〇五年、平成十七年度でございますけれども、この時点で見てみますと、七千三百七十二人の入学者の中で女子学生が二千三百七十四人、割合にいたしまして三二・二%ということで、一一・九%ほどポイントの増加を示しているところでございます。
- 井上哲士君
一九六五年の時点ではわずか一〇・三%なんですね。今、実に三割。
女性の進出自身は大変すばらしいことだと思いますし、また医師不足が深刻な産婦人科や小児科に希望する方も大変多いということであります。ただ、やはり女性医師は出産とか育児という場面で一定の制限や中断を余儀なくされる場合が少なくありません。そうなりますと、医師総数が同じでありますと、要は現場のマンパワーとしては不足をせざるを得ないという状況も出てまいりますし、厳しい労働条件の中で辞めざるを得ないという状況もある。このこと一つ取っても私は定数削減ということは見直しがされるべきだと思います。
もう一つ、労働条件の問題です。非常に今、深夜、交代制の過酷な労働実態の中で、医療事故も後を絶ちませんし、研修医の過労死ということも相次いで起きました。厚生労働省として医師の労働基準法違反について調査、指導をされていると思いますけれども、その結果を御答弁願います。
- 政府参考人(松井一實君)
医療機関の監督状況でございますけれども、医療機関におきまして、特に宿日直勤務、こういったものにかかわる問題が監督署に対しまして申告が出てくるとか、あるいは報道機関などで取り上げられ社会的な問題になりつつあったというふうな状況がございまして、実は平成十四年以降に宿日直勤務の適正化を図るという観点から各般の取組を進めてまいりました。
その取組の一環といたしまして、平成十五年度から十六年度にかけまして五百九十六の医療機関に対しまして個別に監督指導を行いました。その結果、四百三十の機関におきまして何らかの労働基準関係法令違反というものがございましたし、二百四十九の機関では宿日直の許可基準を満たしていないというふうな状況がございました。
こういった違反とか法違反につきましては、まず是正を図らせるとともに、宿日直勤務に係る許可基準、これにつきましては遵守をするようにということで、今粘り強く指導を行っているところでございます。
- 井上哲士君
約四分の三の医療機関でこの基準法違反があったということです。今、厚生労働省は同じお役所なわけですけれども、一方でそういう労働基準法違反の実態の上に献身的な医療関係者の奮闘の上に医療が成り立っているという状況でありますけれども、アメリカなどは医療事故多発の原因を医師や看護師の過労と分析をして定数の見直しなどをしてきているわけです。
いろんな若い医師の状況などを見ましても、やはりこの労働基準法の遵守ということが今後必要でありますし、さらに、病気の複雑化、インフォームド・コンセントの強化、これも患者当たりの時間を増やすということになっているわけですから、私は諸般の事情からいいますとこの定数の見直しは当然だというふうに思います。
同時に、厚生労働省としての結果待ちになるのではなくて、文部科学省として、医師不足の解消、特に地域医療をどう守るか、それから産婦人科や小児科をどうするのか、こういう対策を考えるべきだと思います。
地域ごとの入学定員の在り方、それから医学教育をどう改善をしていくのか、この点での文部科学省としてのお考え、そしてその上で、全体としての医師不足を解決するための大臣の御決意をそれぞれ聞いて、質問を終わりたいと思います。
- 政府参考人(石川明君)
まず、私の方から我が省関係の対応策について御説明をさせていただきたいと思います。
地域における医師不足、あるいは産科、小児科等の特定の分野の医師不足等指摘されておりますが、大変大きな問題であると認識しております。
現在、大学の医学教育におきましては、委員も御案内と存じますけれども、医学生が卒業までに最低限履修をすべき内容を定めました医学教育モデル・コア・カリキュラムというものがございます。これに沿いまして、地域医療、小児科、産科領域、これについても必要な知識、技能、態度、これを修得するための内容が定められておるわけでございますけれども、各大学におきましては、これにのっとりまして、これらの分野の重要性に関する教育を含め、カリキュラムの改善充実に努めているところでございます。
また、先ほどお話がございました入学定員内に県内の高等学校卒業生を対象といたしました入学者枠、いわゆる地域枠でございますけれども、これを設ける動きも出てきております。これも地域の医師不足問題の対応策の一つであろうかと私どもも考えております。平成十七年度は国公私立七大学において実施されておりましたものが、平成十八年度からは新たに国立九大学において導入されるなど、実施大学も着実に増加の様相を見せているところでございます。
一方、文部科学省におきましては、平成十七年度から地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム、こういったプログラムをスタートさせておりまして、国公私立大学が地域医療ですとかそういった医師偏在の問題を担う医療人を養成するために行う特色ある優れた取組に対して重点的な財政支援を行っているところでございます。平成十八年度には、特に医師不足が著しいと言われております小児科、産科などに焦点を当てましてこの事業をやりたいと思っております。
そして、平成十七年の五月からは、先ほど大臣の方からも御紹介申し上げましたけれども、医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議、こういったものも設けまして、今後の医師養成の在り方などについて検討を行っているところでございます。
引き続き、厚生労働省や総務省とも連携をいたしまして、地域医療に貢献する医師の養成につきまして積極的に取り組んでまいりたいと、このように考えております。
- 国務大臣(小坂憲次君)
今答弁させていただきましたように、文部科学省といたしましては、厚生労働省、総務省ともしっかり連携を取りながら、適正な医師配置について更に努力を重ねてまいります。
|