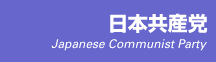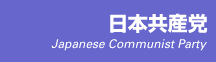|
2007年5月22日(火)
文教科学委員会
「少人数学級の実現」について質問(対総理)
- 財務大臣の諮問機関が、公立小中学校の統廃合が経費節減効果があることを強調し、統廃合の推進を強調したことに対し、文部科学大臣の見解を質す。また、日本の教育予算の割合が先進国の中で最低であること、そのもとで、父母からも教育関係者からも要望が強く、効果も確かめられている少人数学校が地方自治体で広がっているにも関わらず、国の制度として実施することに背を向けていることについてただす。
|
- 井上哲士君
日本共産党の井上哲士です。
教育を何とかしたいというのは、国民の皆さん、今日はテレビをごらんの皆さんも共通の思いだと思います。政治がこの思いにどうこたえるかというのが問われておりますし、そのために今政府が一番やらなくちゃいけないことは、教育にしっかりお金を掛けて、そして国民のこの願いにこたえる条件を整えることだと思います。
しかし、私、今朝ちょっと新聞を見て心配になったんですが、こういう記事が出ておりました。公立小中学校の統廃合加速をという記事でありまして、財務大臣の諮問機関の財政制度等審議会が六月の初めにまとめる報告書の中で、小中学校の、公立小中学校の統廃合が経費削減効果があるということを強調をして、これを加速をするということを打ち出すと、こういう記事なんですね。
そこで、文部科学大臣にお聞きするんですが、文部科学省は、小中学校の統廃合は経費節減のために必要だと、こういうお考えでしょうか。
- 国務大臣(伊吹文明君)
まず、教育的見地からいって、やはり子供はある程度集まって、そしてお互いに多様な子供たちの集団の中で育っていくというのが一番いいと、これはまず大前提だと思います。
それから、先生も私も同じ京都出身ですが、京都市内などでは、昔は、人口が非常に多いときは百メートル間隔で小学校がございますよ。そういう小学校はやはり統合して、そこで余った国民負担を有意義に使えるということは、私はあって当然構わないと思います。ただ、通学に全く無理な状況の小学校を統合する、財源の理由だけで統合するということはあってはならないんで、こういうことの判断はやっぱり一面的にはできませんですよね。現場に即して、財政的な見地から統合しちゃいけないというのも困るけれども、しかし近距離であるのに統合して財源を出すということも、また私はあっていいことだと思います。
- 井上哲士君
 画像をクリックで拡大表示されます。
画像をクリックで拡大表示されます。
| 国名 |
学級編成基準 |
備考 |
| 日本 |
40人 |
|
| アメリカ合衆国 |
24人から31人 |
ケンタッキー州の例・上限の人数 |
| イギリス |
30人 |
初等学校1・2年・上限の人数 |
| イタリア |
25人 |
最大の人数 |
| ドイツ |
24人 |
標準の人数・範囲は18人から30人 |
| ロシア |
25人 |
上限の人数 |
| フィンランド |
24人 |
|
これまで文部科学省は、あくまで教育環境の整備が目的なんだということを言われておりました。今も、経費削減だけを理由にこれは良くないということだったと思うんですね。
私、これ聞きますのは、どうも経費を削減をするということを優先をして教育の問題が考えられているんではないかと。実際、日本の教育の予算が大変貧困だということは今日の議論でも様々出されました。
私も表を作ってまいりましたが、(資料提示)今日の議論にもなっておりましたいわゆるOECD、世界の資本主義国三十か国が集まっている中で、教育にどれだけ予算をつぎ込んでいるか、国民総生産に対する教育費の割合でありますが、日本は三・五、フィンランド六・〇、フランス五・八、主な国だけを挙げましたけれども、三十か国の中で日本は最下位、前回の調査ではびりから二番目、九五年はびりから三番目でしたから、むしろ下がってきたと、こういうことになっております。
総理は、世界最高水準の教育を目指すと、こう言われるわけです。しかし、こういう貧困な予算のままで実現をできるとお考えなんだろうか。世界一の教育を目指すと言うならば、予算もやはり世界水準に引き上げるべきではないか。
去年、この問題での議論のときに、世界に比べ遜色ないという答弁もあったわけですが、内閣の最重要課題だと位置付けた今日も同じお考えなのか、お聞きしたいと思います。
-
- 内閣総理大臣(安倍晋三君)
この予算の比較につきましては、いろいろな角度から見ていく必要もあると、このようにも思うんですね。
OECDの調査によれば、二〇〇三年における我が国の学校教育費に対する公財政支出の対GDP比は三・五%でありまして、OECD平均は確かに五・二%と、このようになっています。我が国のGDP比は、これは世界第二位の規模でありますが、GDPに対する一般政府の総支出の割合は小さいわけでございます。そういう意味におきましては、我が国の政府の支出というのは、他の国々と比べて、総支出はGDP比小さいということでございます。
そしてまた、その中で、教育支出の占める割合、この政府支出の中におきます教育支出の占める割合は英、仏、独並みであるということでありまして、単純な比較は困難ではないかと、こう思うところでございます。
いずれにいたしましても、今後、真に必要な教育の予算については財源の確保のために努力をしていきたいと考えております。
- 井上哲士君
単純な比較と言われましたけれども、現実を比較する必要があると思うんですね。
学力世界一と注目を集めていますフィンランド、日本の約倍ありますけれども、ここでは幼稚園から大学まで授業料は掛かりません。義務教育は二十五人以下学級。これに比べて、日本は四十人学級。そして、学費が高くて高校や大学を泣く泣くやめなくちゃいけないという、そういう子供たちもいるということなんですね。私は、この現実を見れば、とても今遜色がないという状況にはないと思います。
そして、真に必要なお金ということで言えば、今私は、大変大事なのは少人数学級だと思います。勉強を丁寧に教えるという点でも、それから子供の悩みに細やかにこたえるという点でも大変重要な制度だと思いますが、文部科学大臣、お聞きしますが、今ヨーロッパ等でこの小中学校の学級編制がどのようになっているでしょうか。
- 国務大臣(伊吹文明君)
小学校で見ますと、平均的な学級規模は、イギリスは二十六人、それからドイツは二十二人、日本の場合は二十八・五人、これはOECDの調査でございます。
それから、国公立の中学校の平均の規模は、イギリスは二十二・五人、フランスは二十四人、ドイツは二十四・七人、日本は三十三・七人という数字になっております。
- 井上哲士君
私、学級編制の基準を聞いたんですが、今平均を答えられました。なかなか答えにくいからそういう答弁になったのかもしれませんが、学級編制の基準でいきますと、アメリカ二十四人から三十一人、イギリス三十人、イタリア二十五人、大体三十人以下ということになっておりまして、日本の基準は四十人なんです。大きく違うわけですね。
しかし、今、日本でも地方自治体が努力をしておりまして、何とかこの欧米並みのこういう学級編制にしようということで独自の努力がされておりまして、既に東京を除く四十六の道府県にこれが広がっております。地方も国と同様に様々困難があるのに、なぜこういうふうに広がっているかといいますと、やはり非常に国民の要求が強い。そして、教育的効果があるわけですね。
これは、二〇〇五年にある民間教育団体と新聞社が行った調査でいいますと、これは保護者の声でありますが、教育制度に関する改革への賛成で一番多いのが一クラス当たりの子供の人数をもっと少なくすると、実に八一・九%です。それから、実際にこの少人数学級を実施した学校に文部科学省が調査をしておりますが、総じて児童生徒の学力が向上した、それから授業でつまずく児童生徒が減った、これ小学校では九八・七%と、こういうふうになって、非常にやはり効果を発揮をしているわけですね。
そこで、総理にお聞きをいたしますが、保護者も教育関係者も、そして地方自治体もやはり圧倒的に支持をしているわけですから、こういう少人数学級への学級編制に国として踏み出すべきだと思いますけども、いかがでしょうか。
- 内閣総理大臣(安倍晋三君)
この学級編制の在り方については、学級編制の標準を全国一律に引き下げるという画一的な取組ではなくて、地域や学校の実情に合わせた柔軟な取組を可能にしながら、これまで進めてきた少人数教育を一層充実をしていくことが効果的ではないかと考えます。
今後とも、学級編制に係る国の標準は維持をしながら、その上で地方の取組が進むように努めていかなければならないと考えております。
- 井上哲士君
地方の取組進んでおりますけれども、結局一部の学年にとどまっているんです。それは財政的背景がないからなんですね。そこをちゃんと国が私はフォローするべきだということを申し上げているんです。
中央教育審議会でも少人数学級については議論をされてまいりまして、一昨年五月の議事録などを見ますと、これは国がやるべきであって、自治体独自で雇う短期講師は費用に見合う効果が少ない、少人数学級は生活指導に効果がある、安上がりでやろうという考えはこの機会に改めるべきだと、こういうような議論もされておりまして、一人を除き全員が少人数学級賛成だったと、こういうことになっております。そして、これを受けて文科省の調査協力会議も開かれまして、その年の報告書では、小学校低学年ではせめて三十五人学級をという提案もしております。
文科大臣に確認をいたしましたが、中教審でこういう議論があり、こうした報告書も出されているということで間違いないでしょうか。
- 国務大臣(伊吹文明君)
流れとしては、先生がおっしゃったことで間違いないと思います。
ただ一つ、先生、申し上げておきたいのは、地方は人口が減り、児童がどんどん減っていくんで、むしろ子供がいないから結果的に少人数学級になっているんですよ。財源だけでやるんであれば、一番自主財源の多い東京都がなぜ四十人学級を維持しているんですか。ですから、今、地方交付税の算定上は四十人、そして我々の義務教育国庫負担金の計算上も四十人ということになっております。
しかし、将来は努力をして、まずこれを三十五人に引き下げていくという方向で中教審は考えておられますから、私たちもその方向で努力はしたいと思っておりますが、財源があるから地方がやっているわけじゃ先生ないんですよ。地方は人口が少ないからそうなっているんですよ。
- 井上哲士君
私はそんなこと言っておりません。財源があればもっとやりたいのに、国の財源の裏付けがないから一部にとどまっていると、こういうことを申し上げているんですね。
今申し上げましたように、中教審などでもそういう議論が行われましたし、文部科学大臣が少人数学級必要だということを国会での答弁でも当時ありました。
ところが、この流れが変わるんですね。二〇〇五年の六月に経済財政諮問会議に当時の文部科学大臣と中教審の会長が呼ばれまして、中教審会長は小一、小二は三十人学級にすべきだと、こういう発言をしておるわけでありますが、参加者からは様々これに対して閣僚などから批判があり、そして続く財政制度等の審議会で、少人数学級編制を教育水準の向上と同視するという安易な発想は排すべきだと、こういうことが言われ、そして昨年の行革推進法で、この五年間で一万人もの削減ということが教員にまで枠が掛けられると、こういうことになってしまったわけですね。
私、総理、先ほど申し上げましたように、少人数学級についての効果は非常にはっきりしております。要望も非常に強いんですね。真に必要なところにお金をと言うのであれば、私は真っ先にここにするべきだと思います。
日本はOECDの中でも一番予算を使っていないわけでありまして、ここはやっぱり切り替えると、そしてこういう声にこたえるということが必要だと思うんですね。保護者も教育関係者も中教審もこういう声を上げたときに、結局、官邸の司令塔と財務省がこれを止めたわけですから、これはもう総理の責任でこれを切り替えていくことが必要だと思います。
是非少人数学級の実現に踏み出すと、こういう決断を求めたいと思いますが、改めていかがでしょう。
- 内閣総理大臣(安倍晋三君)
先ほどの答弁の中でも申し上げたんですが、GDP比でいえば政府の一般総支出との比率においては、総支出というのは日本は少ないわけでございます。ですから、この支出全体を増やしていくためには、この歳入をこれは図っていかなければならない。それは言わば財源になっていくわけでありますが、ですから、この財源の手当てを我々も責任ある立場として常に念頭に置かなければならないというのは、これは我々が言わば責任を背負っている以上課せられた使命でもあると、このように思うわけであります。
その中において、いかに必要な人材を確保しながら、また、先生方が子供たちと向き合う時間を確保していくかということにおいて努力をしてまいりたいと思っております。
- 委員長(狩野安君)
時間です、時間です。
- 井上哲士君
時間ですので終わりますが、やはり国民も教育関係者も望む方向に背を向けるようでは、そして子供や学校に命令だけ強めるという方向では教育は良くならない。我々は、教育条件の整備のために全力を挙げると申し上げまして、質問を終わります。
|