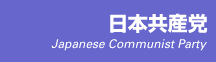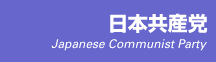|
2004 年 5 月 11 日
法務委員会
裁判員法案・刑事訴訟一部改正案
(第1回目の質問)
- 裁判員制度において国民が司法へ参加することの意義を指摘。密室での取調べなど現在の刑事司法の問題点を示し、捜査の可視化などを強く求めた。
|
- 井上哲士君
日本共産党の井上哲士です。
本会議に続いて質問をさしていただきますが、朝からの審議にありますように、裁判員制度が本当に国民にとって実のあるものにする上でこの参議院での議論が大変大事だと思っております。裁判員制度に今後参加をしていく皆さんが、当時、国会ではどういう議論がされたんだろうかということで議事録をごらんになる方もいらっしゃる。そのときに本当に分かりやすい議論がされているということが大事だと思うんですね。
先ほど、プロの意識改革が必要で、難しいことを難しく言う傾向があるということが言われましたけれども、むしろ簡単なことを難しく言うという場合も結構多いなということを私はこの委員会で思うんです。是非、国民に分かりやすい言葉での答弁を、とりわけこの法案での審議ではお願いをしたいと思います。
本会議でも申し上げましたけれども、この裁判員制度が、長く職業裁判官が独占をしてきた日本の裁判制度に国民が参加をするという点で大変大きな意義があると思っております。そして、そういう改革の実を上げるためには何を改革すべきなのかと、現状はどうなのかと、このことの認識というのが私は土台になると思います。
本会議でも、日本の刑事裁判が有罪率九九%で世界でも突出をしているということを挙げました。そして、その下で少なくない冤罪事件も生んできたし、捜査段階で自白をしたけれども、あれは強要されたんだということで公判で否認をされるという場合も少なくないということも指摘をいたしました。その上で、現在の刑事司法の認識を大臣にただしました。大臣からは、基本的に国民の信頼を得ているという答弁でありました。私も、国民の多数が今の日本の刑事裁判に不信感を抱いているとかそういうことを言うつもりはございませんし、法治国家としてそういうことはあってはならないことかと思います。
ただ一方で、午前中の審議にもありましたように、刑事裁判にかかわった皆さんからは、例えば絶望的という言葉もありますけれども、様々な問題が指摘をされてきました。そして現に、世界に例を見ないあの免田事件のような、死刑確定事件での再審無罪になった例などもあるわけです。こうした少なくない冤罪事件などが発生してきた、こういうことからどういう教訓を酌み出されているのか、まずこの点を改めて大臣にお聞きしたいと思います。
- 国務大臣(野沢太三君)
刑事事件で、正に今委員御指摘のとおり、有罪か無罪か、しかも死刑を含めての御議論をこれから考えていかなきゃいかぬということになりますと、大変この今行っております議論は重い課題をしょっておるということは私もよく認識をしておるところでございます。
今委員御指摘の無罪判決が言い渡された事件で、しかもそれが冤罪として後で修正されたと、こういったのも幾つかあるわけでございますけれども、その内容、理由については様々でございますが、起訴処分について申し上げますと、検察官は刑罰権の実現が国家的な問題であり、かつ検察官には公益の代表者の立場から実体的真実を追求することが求められていると。これは、従来から、自ら被疑者を取り調べるなど所要の捜査を遂げ、収集された証拠を検討し、有罪判決を得ることができるとの高度の見込みがある場合に初めて起訴を行うということの中で裁判をこれまで実行してきたと承知しておるわけでございます。
もとより、この結果としまして検察官の主張が認められず無罪判決が言い渡されて確定する場合もありますが、その場合においては、無罪判決等において指摘された問題点を踏まえまして、検察当局としても更に客観証拠の収集に努めるとともに、取調べに当たっては自白の任意性や信用性の確保に努めるなど、捜査が適正に行われるよう努力しているものと承知をいたしております。
あくまで証拠をしっかり集める、そして適切な法令の適用を図ると、ここに更なる努力を費やすべきだということで、今後とも冤罪等の発生がないように努力をしなければならない、心して取り組む最大のポイントであろうと思います。これは制度がどのように変わりましても、この基本については変わりはないと考えております。
- 井上哲士君
心して取り組む最大のポイントだと、こういう答弁でありました。
ただし、問題は、こうした幾つかの冤罪事件の中で、やっぱり警察や検察の言わば不当な捜査などによって起きたものが幾つか指摘をされております。
例えば八五年の七月に徳島地裁で、初めて死後、被告人が死後に再審をされ、無罪になったという徳島ラジオ商殺し事件という有名な事件がありますが、これは、有罪になった決め手は店員の証言であったわけですけれども、その後、判決後に検事の誘導、強制によってうその証言をしてしまったと、こういう告白をいたしまして、そしてその後、再審が開始をされ、無罪が宣言されました。この二人の店員は、その後、そのうちの一人は告白の手記の中で、自分は途中で過ちと思ったけれども、もし証言を取り消せば偽証罪になると、こう思わされたので公判廷において偽証を続けてしまったんだと、こういうことを手記の中で告白をしております。
それから、これは昭和五十七年の一月に最高裁で有罪の判決破棄になった鹿児島夫婦殺し事件というのもありますが、これも、判決の中では警察による証拠の捏造というような問題も指摘をされております。
それより前で言いますと、いわゆる松川事件で諏訪メモという、被告人に有利な証拠を隠したという問題も指摘をされていると。
こういう警察や、警察によって事実上作られたようなこうした一連の事件というものについてはどういう反省を法務省としては持っているんでしょうか。
- 政府参考人(樋渡利秋君)
先ほど法務大臣からも答弁がありましたとおり、具体的事件におきまして無罪判決が言い渡される理由は様々でございますが、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、無罪の判決が確定した事件又は有罪の判決が確定した後に再審で無罪となった事件につきまして、裁判書及び訴訟記録等を精査するなどして捜査及び公判並びに再審の具体的経過に照らしながら、物証を発見、収集した状況やその鑑定状況等の物証にかかわる捜査の観点、供述の変遷や裏付け証拠の有無等の供述の任意性、信用性にかかわる捜査の観点、事件発覚の端緒から事件を検察官に送致するまでの司法警察員等による捜査の観点、公判における立証の観点、再審請求審及び再審公判における対応の観点等のあらゆる観点から問題点を吟味し、これらにより把握しました問題点を踏まえ更に客観証拠の収集に努めるとともに、取調べに当たっては自白の任意性や信用性の確保に努めるなど、捜査が適正に行われるように努力してきているものと承知しております。
- 井上哲士君
幾つかの事件挙げましたけれども、過去の話で済まないことであります。
昨日、東京地裁で、通勤電車で痴漢行為をしたという、と言われる元会社員の男性に無罪判決が出されました。報道によりますと、本人は電車のドアに挟まったコートを必死に出そうとしていたと、それを若い OL が見ていて痴漢ではないと言ってくれたと。これは冤罪だということを訴えたわけですね。そして、結局その人が、目撃者が出てきて無罪になったわけでありますが、男性は報道によりますと、検察と、検察にも事情を説明したけれども調書に残してもらえなかったと、拘置所は、拘置は約五か月に及んだと、こういうことでありました。報道では、次席検事の方が反省すべき点があると言われたということは昨日言われておりましたけれども、現に今もこういうことがあります。
私は、やはり冤罪というのは一件たりとも起きてはならないことだと思うんですね。こうした、しかし不幸なことが起きてきた、こういう問題を抱えてきた日本の刑事司法に裁判員という形で国民が関与をするということ、そして国民の一般的な常識が刑事司法に反映させられるということ、これが今回の裁判員だと思うんですが、その国民の一般常識が反映するということの意義については、大臣、これはどうお考えでしょうか。
- 国務大臣(野沢太三君)
死刑再審・冤罪事件の反省という点では、国民の良識を刑事司法に反映させることは大変これ意義があると、委員御指摘のとおりだと思います。
様々な現在の裁判制度に関する御批判、御意見があることは承知をしておりますが、私はこの裁判員制度の導入によりまして、広く国民の皆様が裁判に参加する、それによって今まで御議論いただいていますように、証拠の取りそろえ、あるいは論点の整理、そして事前の問題点の検討と、こういった事柄を通して私はこの冤罪に関してもその可能性といいますか、間違いを起こす機会というものは確実に減っていくんじゃないかなと、こう思っております。
やはり、何といいましても、分かりやすく、速く、そして公平にやろうというこの趣旨からいたしましても、この制度はやはり間違いを正す、やはり大勢の人が判断をする、いろんな違った目で物事を見て考える。このことは、やはりこの冤罪事件に関しても、直接的に響くかどうかはともかくといたしまして、大きな意味では大変これ効果のある制度ではないかと期待をいたしておるわけでございます。
- 井上哲士君
間違いを起こさないということに期待をしていると、こういうことでありました。その上でも大事なことは、やはり刑事裁判の原則というのが本当に貫かれることだと思います。
確認をいたしますけれども、疑わしきは被告人の利益にと、こういう刑事裁判の大原則というのは当然この裁判員制度の下でも堅持をされると、これはここでよろしいですね。
- 政府参考人(山崎潮君)
疑わしきは被告人の利益という刑事司法の大原則でございますけれども、これは直接成文法に規定があるというわけではございませんで、いろんな解釈から出てくるということになるわけでございますけれども、この法案では、裁判員は職務遂行に関する一般的な義務として、「法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。」としているわけでございますので、その法令の解釈等も当然ここに入ってきますので、この原則は当然適用があるということになろうかと思います。
- 井上哲士君
当然適用されるということでありますが。
問題は、現在の裁判にこの疑わしきは被告人の利益にという原則がしっかりと貫かれているかどうかということだと思うんですね。私も元裁判官の方等からお話を聞く機会もありますけれども、ずっと刑事裁判にかかわっておりますと、裁く側、言わば検察の側からのバイアスが掛かってしまうと、こういうことをお聞きをすることがあります。
最近、元水戸地裁の所長で東京高裁の判事部総括を経験された木谷さんという法政大学の教授が「現代刑事法」に大変興味深い文章を書いておられました。こう言われているんですね。
この疑わしきは被告人の利益にという立場に忠実であろうとすれば、起訴された被告人が一見犯人らしく見える場合でも、合理的疑いを超えた立証がされたと認められない限り無罪の判決をしなければならないと。これは、社会秩序維持の役割をも担う裁判官にとって、かなりの心理的負担となると。そのため、被告人が虚偽の弁解をしていたり、訴訟外で怪しげな言動をしていたりすると、証拠は足りないが実際は犯人に間違いないのではないかという考えが頭をもたげてくると。しかし、そういう考えでする刑事裁判は、えてして冤罪につながりやすい。これは経験の教えるところであるということを、自らの刑事裁判にずっとかかわってきた経験として言われております。
こういう、言わばプロとしてかかわってきたときに、裁く側のバイアスが掛かってしまう、こういう指摘についてはどのようにお考えでしょうか。事務局長。
- 政府参考人(山崎潮君)
ちょっと私、その論文読んでおりませんのでその詳しい内容は分かりませんけれども、少なくとも裁判官は法と証拠に従って裁判をするわけでございまして、そういう観点からバイアスが掛かるというのはちょっと私も余り納得はできないところがございます。
やはり、それは個々の方の感じ方によるわけでございますので、その点について私はとやかく申し述べるつもりはございませんけれども、今回この裁判員制度を導入したというその視点につきましては、今申し上げた、そういう指摘されたようなことに対応するのではなくて、裁判、基本的には順調には行っておりますけれども、時代の変化とともにやっぱり周りが要求するものが変わってきているわけでございます。それから、個々に見れば、それはいろいろな問題点もあるということでございまして、そういう点を解決をするという観点からこの制度の導入をさせていただいているわけでございまして、ただいま言われたような点からそれを解消するためにこの制度を導入すると、そういうものではないというふうに理解をいただきたいと思います。
- 井上哲士君
ちょっと最高裁にお聞きをいたしますが、疑わしきは被告人の利益にというこの刑事裁判の大原則というのは当然選ばれる裁判員の方々にきちんと説明をされなくてはいけないと思いますが、それはどの機会にどういう形で説明をされるんでしょうか。
- 最高裁判所長官代理者(大野市太郎君)
疑わしきは被告人の利益という、これは刑事裁判の大原則であります。この点についてきちっと理解をしていただくということがやはり裁判員にとって極めて重要であるというふうに私ども思っております。
その機会、いつどのような方法で行うかということにつきましては、一番裁判員がその点を理解し分かってもらえる場面というところできちっと行う必要があるだろうと思っております。それが一回で済むのか、場合によっては、事案によっては何度か行うということも考え得るところだろうと思っておりますので、今後どの場面でどのような方法で行うのがいいかという辺りを実際の運用を頭に置きながら考えていきたいというふうに思っております。
- 井上哲士君
私は、大原則ですから言わば審理に入るまでにこの点は徹底をするべきだと思うんですが、例えば選ばれた直後の説明とか、そういう最初の段階でするべきだと思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。
- 最高裁判所長官代理者(大野市太郎君)
一つの考え方としてそういう選択肢、十分あり得るだろうと思います。
先ほど申し上げたように、どこで一番説明するのが分かってもらえるかというところをもう少し詰めて考えてみたいと思っておりますので、いずれそういったことについても私どもとして十分な検討をしたいというふうに思っております。
- 井上哲士君
先ほど山崎局長の答弁がありましたけれども、衆議院なんかの答弁を見ておりますと、やはりプロは物の見方がだんだん狭くなってくると、そこに国民の常識が入ることが大変大事だということを答弁もされているかと思うんです。
先ほどの木谷さんの結論というのは、裁判所はあくまで常識、換言すれば健全な社会通念に従い素直な判断をすべきであり、証拠の不足や想像を、憶測で補うようなことがあってはならないと、こういうことを述べられて、裁判員制度の発足を間近に控えた現在、このことは一層強く意識されるべきであると、こういう結論なんですね。
私はやっぱり、改めてこの裁判員の方に疑わしきは被告人の利益ということをいろんな場面で今徹底をするというお話がありました。そういうことを議論をする中で、とかく物事の見方が狭くなりがちだというプロの方が、国民の常識と共同する中で、言わば裁く側に知らず知らずのうちに偏ってしまったような見方も正していくと、こういう契機に私はこの制度をするべきだと思うんですけれども、改めて答弁をお願いします。
- 政府参考人(山崎潮君)
先ほど私申し上げたのは、長くやっていると検察のバイアスが掛かると、そういう見方については私はちょっといかがかというふうに申し上げておりますけれども、ただ私、元々この制度を考えるときに、非常に裁判というのは、裁判官というのはなかなか外へ出て自由に行動できない制約もございます。そうなりますと、物事を一定の方向から見るということになるわけでございます。物事が自分の見えている面を見るということでございますけれども、じゃ、その裏側は本当に見られるかということになりますと、なかなかそこまで目が行き届かない、あるいは見る範囲も長年仕事をやっておりますとどうしても狭くなってくると、こういうことになるわけでございます。
それで、このまず弊害を取り除かなければならないということから、今法案として御承認を得たく、得るべくこの国会に提出しておりますけれども、判事補あるいは検事を二年間弁護士として職務をさせて、それで元へ戻すという、こういう制度を提案させていただいておりますけれども、まずそういう点で裁判官は外に出て物事の裏側もちゃんと見るようにということでございまして、それがまず必要であろうということでございます。
ただ、これは二年という限られた期間でございますので、それだけでは十分ではないということでございますので、そこで国民の方に裁判の中に入っていただいて、裁判官から見る物の見方、それだけではないということもその中に反映をさせていただいて、それで常識的な落ち着きのある判決、これをすることによって国民にも司法が納得してもらえるものになると、こういうことからこの制度を導入するということでございますので、言われている点が似て非なるものだというふうに考えております。
- 井上哲士君
私は、繰り返しになりますけれども、やはり国民の健全な常識が裁判にかかわるということが、やはりいろんなところから指摘をされてきた日本の刑事裁判の問題の改善につながるものでなくちゃいけないし、そういうものとして作られていく、改善もされていくということを強く求めておきます。
その上で、幾つか具体的な点について質問をいたします。
本会議でも、この裁判員制度がその意義にふさわしいものになるためには二つの柱が必要だということを述べました。一つは実質的に裁判員の方が裁判に参加できるような制度にすること、それからもう一つは参加しやすい、参加したくなるような制度にすることが必要だということでありますが、まず実質参加という点についてお聞きをいたします。
この点で、繰り返し合議体の構成ということについて質問をしてまいりました。やはり裁判員が自由に発言をプロの前でできるようにするためには、この問題は非常に大事だと思っております。例えばイタリアでは、戦後、国民の意見をより反映させようということで、参審員の数を五人から六人に増やしております。我々は裁判官一名に裁判員九名が必要だということを提案をしておりますが、少なくとも裁判員は裁判官の三倍は要るというのが多くの関係者からも出されております。この間、この問題を議論いたしますと、通常の合議体が裁判が三人で行われると、それとの整合性ということを盛んに言われるんですが、例えばイタリアなどは通常の裁判は三人、そしてこの参審制では裁判官が二人に減るという、こういう制度にもなっておるんですね。
ですから、私は、全く新しい国民参加の制度を作るということからは、そことの整合性というよりも、本当にいい制度を作るという点でこの裁判員の数というものをやはり三倍以上ということを考えることが必要だと思うんですが、その点、改めてどうでしょうか。
- 政府参考人(山崎潮君)
イタリアは確かにそのような制度を取っているということでございますけれども、私ども、この制度を導入するに際しまして世界の各国のその在り方等についても研究はいたしました。ただ、私ども、この制度を安定的に進めていくという見地から考えた場合に、現在行われている裁判、これもあるわけでございまして、これについては大事な事件は三人で行っていくと、こういうことでございます。
今回導入する裁判員裁判の対象事件につきましては、現在三人で行われているものの一部分、これを行うわけでございますけれども、残りの部分については裁判員の対象とならない事件も三人でやるということになるわけでございます。そういう関係から、やはり裁判はきちっと裁判官三人で法律問題等を判断して、その上で決めていくというルールが前提になっておりまして、それよりもっと重い事件につきまして、裁判官の数を減らすということが、やはり制度のバランスとしてこれでいいのかという問題は当然出てくるわけでございまして、この裁判員制度の中でも法律の解釈につきましては、これは裁判官の専権になるわけでございます。それから、訴訟手続も同じでございますけれども、この法律解釈の中には憲法に違反するかしないかというような重要な判断も当然に入ってくるわけでございます。こういう判断につきましても、やっぱりきちっと行っていくという点から考えますと、やはり三人の裁判官が必要になると、こういう結論に達したわけでございます。
それと、裁判員の数でございますけれども、これは全体として余り人数が多過ぎるとかえって主体的、実質的に参加をすることができなくなってしまうと。どうせだれかが意見を言ってくれるんだから、それから意見を言う時間もないから自分は黙っているということになるわけでございますので、そういうことにはならないような範囲の人数にしましょうと。
この二つの大きな命題を前提にいたしまして、その中で裁判員の数については最大限多くして実質的に参加をしてもらえるようにというような配慮をしたということでございますので、そこは御理解を賜りたいというふうに思います。
- 井上哲士君
現行制度との整合性を改めて強調されたわけですが、今度の法案では裁判官一人、裁判員四人という制度もあります。この場合も、裁判員制度でなく裁く場合には合議体三人で行われるわけですね。その点でいえば整合性が考慮されていないんではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
- 政府参考人(山崎潮君)
確かに、この裁判員制度の対象になる重大な事件、その中でも、準備手続を経まして争点の有無がはっきりしてくるわけでございますけれども、その中で被告人が事実関係を争っていないという事件、これがございます。その中でも、それ以外にも法律の解釈、あるいは訴訟手続上の問題等、それから情状でございますね、刑の量定についてもそれほど厳しい状況にはならないというようなもの、こういうものは、ある場合には三人と六人という大きな単位のところで判断をする必要はないのではないかということから一人と四人と、こういうものを作ったわけでございます。
これにつきましては、バランスでございますけれども、裁判官は一人でございますけれども、これは法律解釈上の問題等が余り起こらないということをある程度念頭に置きながら考えているわけでございますので、その点では裁判官は一人ということで可能であるということになるわけでございますが、ただ、量刑等の問題についてはどうするかということでございますけれども、量刑についてもやはり複数の目で見るということが必要になってくるということから、裁判官と裁判員、必ずしも同じ形ではないんですけれども、やはり複数の目をもって見るということから四人の方に入っていただいて、五人で量刑についても全体を見ていくということになればそれなりの正しい結論が出てくるんだろうということでその一人と四人という構成を考えたということでございまして、やはり量刑でありましても複数の目できちっとチェックをすると、こういう点の要請は同じであるというふうに考えておるわけでございます。
- 井上哲士君
そういう考え方であれば、私は、複雑な問題であっても一人の裁判官と九人の裁判員、十人の目で大いに議論をするということもあり得るし、それがむしろ必要だということを指摘をしておきたいと思います。
その上で、今度は評決の問題でありますけれども、陪審制や参審制などの場合に、合議体における評決要件というのはヨーロッパなどではどういうふうになっているでしょうか。
- 政府参考人(山崎潮君)
ちょっと主要の五か国の評決要件について御紹介をいたします。
アメリカでございますけれども、連邦の関係では、陪審員十二名、全員一致で決めるということです。それから、イギリスも陪審員十二名全員の一致ということです。それから、ドイツの、地方裁判所でございますけれども、有罪評決は裁判官三名それから参審員二名の三分の二の多数決ということでございます。フランスは、裁判官三名、参審員九名の三分の二以上の判決と。それから、イタリアでございますけれども、裁判官二名、参審員六名の単純多数決という、このようにばらばらに分かれているという状況でございます。
- 井上哲士君
イタリア以外は全員一致ないしは三分の二というのが基本になっております。刑事罰を科すという重大な問題を決めるわけですから、私は当然だと思うんですね。
法案ではこれは過半数ということになっているわけですが、やはり評決要件はそういう既に参審制を取り入れている諸外国の流れなどを見ましても三分の二にするべきではないのか、とりわけ死刑判決という重大な結果をもたらす場合は全員一致にすべきではないのかと、こう思いますが、いかがでしょうか。
- 政府参考人(山崎潮君)
世界の各国はいろんな在り方があるんですけれども、例えばドイツ、今三分の二の多数決というふうに申し上げましたけれども、これは裁判員裁判以外の裁判についても同じルールでございます。世界の各国、いろいろ在り方がそれぞればらばらに分かれております。
私どもの考えた理由は、現在、裁判のルールは全部単純多数決で決めていくということで動いているわけでございます。これは別に刑事に限らず、民事であっても全部そのルールでやるということになっているわけでございます。例えば刑事事件、現在行われていますのも、これは三人の裁判官であれば三対二になりますけれども、これはただ多数決ということでたまたま裁判官の人数の構成がそうだからそうなるというだけでございます。これは最高裁に投影してみますと、十五人の裁判官でございますので八対七ということでの多数決でございます。これによって、死刑であろうとそうでないものであろうとそこで決めていくと、こういうルールを取っているわけでございます。
そうなりますと、そのルール全体の在り方をもし考えるならばまた違う論点が出てくるかもしれませんけれども、現在、そのほかの点についてもすべて問題があるという指摘はございません。したがいまして、この裁判手続を導入するからといってこれだけを特別に扱わなければならないという合理的な理由は私どもはないというふうに考えまして多数決ということを取ったわけでございます。
- 井上哲士君
確かに、現行、過半数ですけれども、先ほどありましたように、高裁にしても地裁にしても合議体は三人ですから三分の二と、過半数といいましてもなっています。それから、最高裁でも小法廷は五分の三ということになるわけですね。ですから、八対七という大法廷というのはめったに行われないわけでありまして、実際的に言えば三分の二のような運用もされてきたという問題もあります。
それから、この裁判員制度自身が広く世界各国で行われてきている、そういうものとして日本でも導入をしていくという中で、やはり今の日本の在り方ということにこだわらず、新しい制度として、そして外国の例も見てやはり三分の二ということを考えることが必要だと思いますけれども、改めていかがでしょうか。
- 政府参考人(山崎潮君)
現段階においては私は過半数、これが相当であるというふうに考えておりますけれども、これをまた運用していって、世界のいろんな例、これもフォローしながら、将来的にどうするかという問題はあり得るかと思いますけれども、ただ、現在においてはこれでスタートをすべきであるというふうに考えております。
- 井上哲士君
次に、評議、評決の在り方についてお聞きをします。
十分な評議を行わないままに評決で簡易に結論を出すということは絶対あってはならないと思いますし、審議会の議論でも、そして検討会の議論でも、原則全会一致を目指すべきだと、こういうことが繰り返し議論をされていたと思いますけれども、原則全会一致を目指すべきだと、この点は確認してよろしいですね。
- 政府参考人(山崎潮君)
基本的にみんなが一致して結論を出すというのは、それは望ましい姿であるというふうに考えます。
- 井上哲士君
そうしますと、そういう原則全会一致を目指して、そしてそのことによってできるだけ多くの裁判員の皆さんが率直に意見を出せるようにする、そういうやはり評議の進め方というものをある程度ルール化をしておくことが必要だと思うんですね。
例えば、裁判員の前に裁判官が意見を言わない、裁判官は最後に意見を言うとか、そういう形で多くの意見を引き出すというやり方が必要かと思うんですが、この運用に当たって、最高裁としてはこの点いかがお考えでしょうか。
- 最高裁判所長官代理者(大野市太郎君)
裁判員の方に積極的に評議に加わっていただいて、裁判員の健全な良識が裁判に反映されるということがこの制度の趣旨であるとすれば、裁判員からできるだけ多くの意見が出される、そして裁判官との間で実質的な意見交換がなされていくということが必要だろうと思います。
ただ、評議といいますのは千差万別といいますか、事案によっていろいろ違います。それから、その評議の中でどなたが一番最初に発言してもらうのがいいかといった辺りも裁判官はそれまでのいろいろな経過を見ながら考えていくことでありますので、そこら辺りのところをルール化していくというのはちょっと硬直化してかえって動きにくくなるのかなという懸念もございます。
そういったこともありますので、今後慎重に検討していく必要があろうかと思っております。
- 井上哲士君
イタリアなどは法文の中に明確なルールがあるようですし、フランスなどでも明文のルールがあると聞いております。硬直的なルールにするかどうかは別として、いろんな方法でのルール化というのは、私は工夫できると思うんですね。
いずれにしても、裁判官が言わば議論を引き回すというようなことがないように、先ほど事務局長からありましたように、本来、やっぱり全会一致を目指して大いに議論をするという本来の立法の趣旨であるとか、それからそういうための評議のガイドライン的なものを作るであるとか、そのための研究、研修をするであるとか、そういうことも必要かと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
- 最高裁判所長官代理者(大野市太郎君)
委員御指摘のとおり、合議において評議を尽くすということは当然であります。実際の運用の場面でも、きちっと評議を尽くして、できるだけ全員が同じ意見になるように議論を進めていくんだろうと思います。
こういった合議において評議を尽くすべきということは、裁判官にとってはこれは現在でもそうですし、これから裁判員が入った裁判でも同様だろうと思います。こういった考えでおりますし、また法律自体がそういったものを予想している、想定している、あるいは期待しているものでありますので、そういった趣旨についてはきちっと周知を図っていきたいと思っております。
- 井上哲士君
その上でちょっと評決についてお聞きをしますけれども、事実認定とか、それから無罪か有罪か、量刑をどうするか、こういうことが、いろいろな評決があろうかと思うんですが、それぞれどういうやり方になるんでしょうか。
- 政府参考人(山崎潮君)
事実認定と量刑についてちょっと分けて現実にどうなるかということを申し述べたいと思いますけれども、まず犯罪事実の認定でございます。
例えば被告人の犯人性というんですか、被告人が犯人かどうかという点について争いがある殺人事件で、裁判員の五人の方は被告人が犯人である、こういう意見を述べたということを前提にいたしまして、裁判官三人及び裁判員の一人、これは被告人は犯人とは認められない、こういう意見を述べたということを前提にしたといたします。刑事裁判におきましては、検察官が犯罪事実の立証責任を負うということにされておりますので、そうなりますと犯罪事実の一部であります被告人が犯人であるということの立証がされているかという点が評決の対象になることになります。
ただいま申し上げた点で申し上げますと、裁判員五人が被告人が犯人であるという意見でありますので、合議体の総数九人の過半数に達していることにはなります。しかし、ここの法案ではそのルールは単純には採用しておりませんので、両者の意見が反映された上の過半数、こういうルールを取っております。
そこで、その五人には裁判官が一人も含まれていないということから、この法案の六十七条一項が要求しております裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数、これにはなっていない、達してはいないということになります。したがいまして、評決によって被告人が犯人であると認定することができないということになります。結局、被告人が犯人であることの立証が十分にされていないということに帰着するわけでございますので、これは判決で無罪の言渡しをする、こういうようなルールになるということでございます。
それから次に、量刑でございます。
量刑について、設例は、裁判員五人が被告人は無期懲役に処すべきであるという意見を述べまして、裁判官の一人が懲役二十年、それから裁判官の二人とそれから裁判員の一人、残りの一人は懲役十五年の刑が相当であると、三つに分かれたということをちょっと想定をしたいと思います。
それで、裁判員五人が無期懲役という意見でございますので過半数には達しておりますけれども、その五人の中には裁判官が一人も含まれていないということになりますので、先ほど申し上げました法案の六十七条二項、この評決の要件を満たさないということになるわけでございます。そうなった場合には、裁判官一人の意見を含む過半数の意見となるまで最も被告人に不利な意見の数を順次有利な方に加えていくという、こういう作業をするわけでございます。その中で最も利益な意見である、そうなりますと懲役二十年の刑について評決が成立をするということになるわけでございます。
こういう手順というんですか、考え方で決まっていくということでございますので、ちょっとやや複雑ではございますけれども、この辺のところを御理解賜りたいというふうに思います。
- 井上哲士君
常に被告人の利益にという形で評決がされていく、こういうことでありますが、先ほどのルールとの関係でいいますと、少なくとも評決に関しては裁判官が自分の意見を述べるのは最後にする、これは明確なルール化をしたらどうかと思うんですが、その点いかがでしょうか。
- 政府参考人(山崎潮君)
この法案でも、裁判長は評議に当たって裁判員の方が十分意見が言えるように、そして適切な審理ができるようにという配慮義務規定ですか、これ六十七条だと思いますけれども、ここで設けておりますので、この規定によりまして、実際の運用も、裁判長はまず裁判員の方に意見を言っていただいて、その上で審議を始めていく、こういうようなことになっていくだろうというふうに予想をしております。
- 井上哲士君
アメリカの陪審などでいいますと、説示というのが行われます。評議に入る前に裁判員の役割とか注意事項とか事実認定の原則など、これは評議の中で逐次やるという説明でありますけれども、むしろ基本的な問題については公判廷でやるということが必要ではないかと思うんですね。
制度は違いますけれども、アメリカの場合は、不適切な説示というのは、これは上訴理由にもなるわけで、やはり評議の基本的枠組みになる事項については公判で行って、やはり検証が可能にするということも必要かと思うんですが、その点いかがでしょうか。
- 政府参考人(山崎潮君)
先ほど、ちょっと訂正させていただきますが、六十七条と申し上げましたが、六十六条の間違いでございます。済みません。
ただいまの御指摘の点については、例えばアメリカの陪審員における説示ですか、こういうものがあるわけでございますけれども、これは事実審理の終結後に、陪審が評議に入る前に裁判官が陪審員に対し事件の法律問題についての説明を与えると、こういうルールがあるようでございます。
こういうような説示に関しましては、陪審員が独立して判断をするのに裁判官が不当な影響を与えないようにという配慮から評議室ではなくて法廷でされる、こういうルールを採用しているわけでございますけれども、裁判官と裁判員が一緒に評議をするというようなルールの場合にはこういうような心配はないわけでございますので、これは裁判の評議の中、こういう中で説明をしていくということで問題はないということから、あえてそういう制度を採用はしていないということになります。
なお、裁判員の選任手続がございますけれども、その最後に、検察官、それから弁護士、この出席の下で裁判長が選任された裁判員あるいは補充裁判員に対していろいろな説明をするということも予定をされておりますので、そういう中で、一般の傍聴人はおりませんけれども、当事者がいる中で一般的なルールの説明をするということも行われるということになりますので、こういう点で、あえて法廷のところでやる必要がないということでございます。
- 井上哲士君
あえて必要ないというお話でありましたけれども、やはり関係者の検証可能な形できちっと示すということが私は裁判への信頼性とかいうことからいっても必要ではないかということを思います。
最後に、いわゆる取調べの可視化の問題について幾つかお聞きをいたします。
本会議でも指摘をいたしましたけれども、否認事件が長期化する要因の一つに、捜査段階での自白の任意性をめぐる争いというのがあります。これが続きますと、正に裁判員制度自身が成り立たないということになると思うんですね。
最近話題になりましたもの、例えばリクルート事件の場合は、大部分の証人が供述調書の記載と異なる証言をしたということが言われておりますが、公判回数三百二十二回に及ぶ事件でありますけれども、被告人質問が三十八回と、やはり任意性、信用性が大きな争点となって、おおむね被告人質問の三分の一程度が取調べ状況に関する質問で、取調べ検事と接見した弁護士が証人になったり、こういうものの開廷数だけでも二十五回になったというふうにお聞きをしております。
こういう自白の任意性をめぐる争いというのが刑事裁判の長期化の一つの原因だと、この認識はよろしいでしょうか。
- 政府参考人(樋渡利秋君)
刑事裁判の長期化との御指摘でございますが、平成十四年の地裁におきます通常第一審事件の平均審理期間は三・二か月間となっておりまして、一部に長期化している事件はございますが、二年を超える長期公判事件はおおむね減少傾向にありまして、検察当局におきましても、昨年成立しました裁判の迅速化に関する法律に基づき、迅速かつ充実した刑事裁判の実現に努めているところと承知しております。
言うまでもなく、裁判に要する期間は事案の内容や被告人、弁護人の防御活動によって異なり、一部の事件について裁判が長期化している原因も、公判期日の頻度の問題や証人尋問等個別の証拠調べに長時間を要する事件もあるなど、個々の事件によって異なり、一概に申し上げることは困難でございまして、御指摘のように、必ずしも自白の任意性をめぐる問題が裁判の長期化の原因であるとは認識しておりません。
リクルート裁判の例を挙げられましたけれども、これからの、これからの裁判の制度には、先ほど来本部の方で説明されておりますように、裁判を、法廷を始める前の準備手続というものがございまして、そこで争点を絞ってやっていこうというわけでございますので、ますます迅速化になっていくだろうというふうに考えております。
- 井上哲士君
日弁連が作られた長期刑事事件の分析という資料を今手に持っておるんですけれども、確かに長期化の要因というのはいろいろあります。
しかし、自白の任意性が争いになった事件というのはやはりかなり長期化しているということは、これからも見て取ることができるんですね。密室で行われていますから、結局、法廷では水掛け論になると。これは非常にやはり長期化をしますし、裁判員にとっては大変難しい判断を求められることになると。そういうことが続きますと、正に裁判員制度自身がもたないということになると思うんですね。
この自白の任意性をめぐるそういう争いをなくしていくということを何らかのやはり制度的手当てが私は不可欠だと思うんですけれども、これはどのような方策を考えていらっしゃるんでしょうか。
- 政府参考人(樋渡利秋君)
お尋ねに関しましては、法務当局といたしまして、自白の任意性に関する審理のために刑事裁判が長期化しているとは認識しておりませんが、裁判の迅速化に関する法律の趣旨を実現するため、迅速かつ充実した公判審理を実現する必要があり、これは裁判員制度が導入された場合、その円満な実施を図るためにも重要であると考えております。
法務省を含めました関係各省庁におきましては、被疑者の取調べの適正を図るための方策として、平成十六年四月一日から、身柄拘束中の被疑者、被告人の取調べの過程・状況に関する事項につき書面による記録の作成、保存を義務付ける取調べ過程・状況の記録制度を実施しており、この制度は、公判において取調べに関する客観的、外形的な証拠資料を提供することにより、公判審理の充実、迅速化に資することも目的とするものでございます。
また、最高検察庁におきましては、平成十五年七月十五日、次長検事を統括責任者とする刑事裁判充実・迅速化プロジェクトチームにおきまして刑事裁判の充実・迅速化に向けた方策に関する提言を取りまとめており、その中で、捜査段階における自白の任意性を主として客観面から担保するため、検察官として留意すべき点としまして、今後導入される取調べ過程・状況の書面記録制度を適正に運用すること、任意性担保に関する資料を整えること、弁護人との接見に関して今後なお十分な配慮をすること、被告人調書の開示にできる限り柔軟に対応していくことを挙げているものと承知しております。
- 井上哲士君
法曹三者の協議会が設けられているわけですが、その中で、例えば今、書面による記録ということがありますけれども、そういうことがどういう効果を上げているかとか、そのことも検証の対象になっていくんでしょうか。
- 政府参考人(樋渡利秋君)
御指摘の法曹三者との協議会というのは、先ほど少し申し上げました、三月に設けました協議会のことであろうと思いますが、今後の裁判員制度の実施に伴いまして、その運用面についていろいろなやるべきことの協議をしていくとともに、今後、将来検討すべき刑事司法制度についての問題点を協議していこうという場でございます。
そういうことに関しまして、今御指摘のような点に関しまして、そういう問題点が出されれば、協議をすることにやぶさかではございません。
- 井上哲士君
可視化をするとなかなか自白が得られない、真実発見ができないということは今日の昼間の議論の中でもありました。
衆議院の参考人の質疑の中で、元日弁連会長の本林さんが、自白がなければ立証できないということになりますと、憲法が黙秘権を定めていることを否定する論理につながると。重要なことは、自白に頼らない立証のスキルを捜査官、捜査機関で身に付けていくことであって、決して取調べを密室化することではないと、こういう指摘をされております。そして、従来はいわゆる取調べ過程の録音、録画というのは専らヨーロッパということでありましたけれども、最近はアジアにもずっと広がっております。
これも、日弁連が韓国とか台湾を訪問をした記録集もいただきました。既に韓国は取調べの弁護人の立会いということが認められてきていて、そして今年五月には録画、録音の試験的実施も開始する予定だと、こういうことを聞いております。日弁連の調査団に、韓国の警察庁の捜査局長が、現代は透明性の要請が増し、隠すことができなくなった時代ですと、このような時代にはすべてを公開することによってこそ信頼が得られると、こういうことを言われたということが言われております。
裁判員制度という新しい制度を導入する中で、世界的にも大きなやはり潮流、流れになっている録音、録画ということについて、やはり足を踏み出すということが必要かと思うんですけれども、改めて法務省の御見解を伺います。
- 政府参考人(樋渡利秋君)
繰り返して申し上げるようで恐縮でございますが、この問題は今後、刑事手続全体の中で取調べの重要性等のことを考慮しながら、いろいろと将来にわたってといいますか、今後検討を続けていきたいというふうに思っております。
- 井上哲士君
先ほどの韓国の調査の資料の中で、直接取調べに当たっている検事、刑事の方のコメントも出ておりますけれども、取調べにおいて被疑者が真実を語るかどうかは弁護人が立ち会っているかどうかとは関係がないということを実際にやり始めたところで言われているわけでありまして、私は、新しいこの裁判員制度が始まる下で、是非前向きな積極的な検討を強く求めまして、終わります。
|