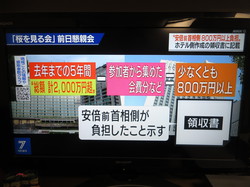衆院予算委基本的質疑二日目。午後から志位委員長が質問に立ち、学術会議任命拒否問題の一点に絞って菅総理を厳しくただしました。朝から、立憲民主党の枝野代表や今井議員、辻本議員らのこの問題での質問が続き、最後に志位さんが質問。菅総理はまともに答えられず、ひたすら、すり替えと逃げの一手でした。
衆院予算委基本的質疑二日目。午後から志位委員長が質問に立ち、学術会議任命拒否問題の一点に絞って菅総理を厳しくただしました。朝から、立憲民主党の枝野代表や今井議員、辻本議員らのこの問題での質問が続き、最後に志位さんが質問。菅総理はまともに答えられず、ひたすら、すり替えと逃げの一手でした。
志位さんは、なぜ、六人の任命を拒否したのか理由を問うことからはいり、理由を明らかにしないままの任命拒否は学術会議の独立性を破壊し、日本学術会議法違反だと追及。さらに憲法が保障した学問の自由の侵害であることを科学者が軍事研究に動員総動員された反省に立って作られた日本学術会議の設立の経緯も示してただし「強権をもって異論を排斥する政治に決して未来はない」と締めくくりました。
まともに答弁できず、たびたび、後ろから秘書官にメモを示され、かみ合わないを紙を読み上げる姿が繰り返されました。自民党席からもヤジも飛ばせない、理詰めの追及でした。
アメリカ大統領選の開票も気になり、予算委中継を見ながら時々開票速報を覗くという一日。大刀りょせんは最後まで激戦です。
 昨日、投開票された住民投票で、大阪市廃止の住民投票は反対多数で再び否決されました。市民の良識の勝利です。今朝の各紙は一面で大きく報道。しんぶん赤旗も東京、大阪では一面で掲載され、若者たちのはじけるような笑顔が躍っています。
昨日、投開票された住民投票で、大阪市廃止の住民投票は反対多数で再び否決されました。市民の良識の勝利です。今朝の各紙は一面で大きく報道。しんぶん赤旗も東京、大阪では一面で掲載され、若者たちのはじけるような笑顔が躍っています。
深夜の記者会見で山中智子日本共産党大阪市議団長が、「これでノーサイド(終了)にして、制度いじりではなく、当たり前の自治体に戻しながら、政令市を残してよかったと思っていただけるよう市民と一緒に市政をすすめていきたい」と涙ぐみながら語られたのが感動的でした。
朝は国対会議。午後に、日英EPAについて穀田、笠井両議院とともに政府レクを受けました。夕方の議員団会議では、大阪をエリアとする山下、清水、大門各議員や、沖縄出身者の多い大正区に入った赤嶺議員からそれぞれ大阪市廃止を否決に追い込んだ取り組みんについて報告がありました。公明党が態度を変え、当初は賛成の世論が大きく上回る中、情報提供型の取り組みん徹し、市民的共同を広げる中で大きな変化を作り出したことが生き生きと語られました。
今日から衆院予算委。午前中の自民党の質疑では学術会議問題で任命拒否には触れずに、会議の在り方にすり替えるひどい質問。午後から立憲民主党の質疑となり、具体的に質しましたが、総理はまともに答えることができませんでした。明日は立憲の枝野氏の質疑から始まり、午後には志位委員長が質問に立ちます。
午前中は参院本会議での代表質問、午後は衆院本会議で代表質問2日目で日本共産党の志位委員長が登壇しました。
志位委員長は質問時間半分以上を使って日本学術会議の任命拒否問題で追及しました法律違反であり、憲法で保障された学問の自由の侵害であることを様々な角度から具体的に質しましたが、菅総理はまともに答えることができず、同じ答弁の繰り返し。明日は参院で小池書記局長が質問にたちます。
参院の代表質問は立憲民主党と自民党。自民党の質問者がわざわざ「総理の内政、外交に渡る国家ビジョンと哲学を改めてご自身の言葉でもう少し国民に詳しく発信を」と求めたのに、総理は「自助、共助、公助、そして絆」という言葉の繰り返しと答弁原稿の棒読みだけ。語るべきビジョンと哲学も自らの言葉も持たないことが露呈しました。
 学術会議問題で午後から第8回ヒアリング。出席された大西元会長は、「推薦通り任命する義務はない」などとした18年の事務局文書の問題点を指摘し、事務局が会長らに相談せずに独自に作成するのはあり得ないことだと述べられました。
学術会議問題で午後から第8回ヒアリング。出席された大西元会長は、「推薦通り任命する義務はない」などとした18年の事務局文書の問題点を指摘し、事務局が会長らに相談せずに独自に作成するのはあり得ないことだと述べられました。
ところが事務局からは今日もこの文書の作成経緯について「確認中」とするばかりで資料提出がありません。さらに追及します。
ICAN川崎哲さんが昨日記者会見を開き、核兵器禁止条約の批准国が23日にも発効に必要な50か国を超える可能性があると述べられました。さあ、いよいよです。
一方、今朝のニュースで米国が、複数の条約批准国に、批准を取り下げるよう求める書簡を送っていたことが分かりました。書簡では「核禁止条約を批准する国家主権は尊重するが、それは戦略的な誤りであり、批准を取り下げるべきだと考える」と強調しているとのこと。
許せないことですが、それだけ彼らがこの条約を恐れている証拠。あらゆる妨害はねのけ発効させましょう。