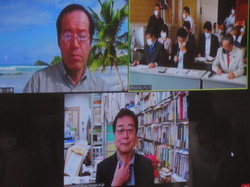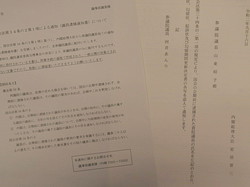菅首相による学術会議人事介入という重大事態をスクープした今朝の「しんぶん赤旗」一面。新しい会員による学術会議の総会が今日から開かれる中、午前中に加藤官房長官が105人の推薦のうち、99人のみを任命したこと、推薦がありながら任命しなかったのは初めてであることを記者会見で認め、大問題とてマスコミ報道が広がろっています。
菅首相による学術会議人事介入という重大事態をスクープした今朝の「しんぶん赤旗」一面。新しい会員による学術会議の総会が今日から開かれる中、午前中に加藤官房長官が105人の推薦のうち、99人のみを任命したこと、推薦がありながら任命しなかったのは初めてであることを記者会見で認め、大問題とてマスコミ報道が広がろっています。明日、臨時国会が召集され、衆参本会議の新しい首相の指名選挙が行われます。昨日、自民党の新総裁に選出された菅氏が与党の多数の支持により首相に選出されることになり、いよいよ「安倍総理なき安倍政治」の継承を打ち破る本格的たたかいがはじまります。
朝から、自民党の新役員や組閣人事についての報道が続きました。一方、午後には新しい、野党の合流新党としての「立憲民主党」の結成大会が開かれ、枝野代表のもとでの新執行部も選ばれました。また、新しい「国民民主党」も結成されました。
今日はこうした動きを受け、朝の国対会議の後、新しい議会構成に伴う様々な問題の打ち合わせや政党間協議などなどを断続的に行いました。
 合間をぬって、憲政記念館で開かれている特別企画展示「館蔵資料と事務局文書で見る議会の歩み」を見に行きました。帝国議会の始まりから戦後の国会の再出発までの激動を当時の貴重な生の文書で紹介しています。1928年に行われた初の普通選挙後の第55回国会の衆院本会議の座席表が展示されており、山本宣治の名前もありました。
合間をぬって、憲政記念館で開かれている特別企画展示「館蔵資料と事務局文書で見る議会の歩み」を見に行きました。帝国議会の始まりから戦後の国会の再出発までの激動を当時の貴重な生の文書で紹介しています。1928年に行われた初の普通選挙後の第55回国会の衆院本会議の座席表が展示されており、山本宣治の名前もありました。
今日の閣議でコロナ対策の予備費三回目の支出が決まり、衆参の予算委理事会で政府から説明を受け質疑がありました。
1.6兆円の規模ですが、コロナ患者を受け入れていない病院でも大幅な減収があるのに補てんの予算は引き続き計上なし。衆院で藤野議員が質問すると「昨日厚労大臣と財務大臣が協議して『引き続き検討』になった」と答弁。必要性があるからこそ大臣同士が協議したはずです。
これ以上先延ばしすれば、医療機関の破綻が広がります。直ちに減収補てんを!
盆明け最初の国対会議。感染が拡大するコロナ問題で、今週行われる衆参厚生労働委員会で取り上げる課題など、議論しました。夕方には、渋谷で公開中の映画「はりぼて」を見ました。
富山のテレビ局が、白紙領収書など富山市議会での政務活動費の不正を暴く発端から14人の市議の辞職と、その後を描くドキュメンタリー。辞職市議らの狡猾で滑稽な姿に観客から何度も失笑が起きました。政治を問い、有権者を問い、ラストシーンでは報道機関をも問います。
議会傍聴や街頭での運動を進める市民の映像には、何人もの私の知人の姿も。全国で順次上映されます。ご覧あれ。
政府与党が憲法53条に基づく臨時国会の召集を要求しているにもかかわらず政府与党が拒否していることについて野党国対委員長連絡会議が開かれ、引き続き召集を求めていくとともに、閉会中審査を開かせるという「二兎を追う」ことで一致。
政府は7日(金)に1兆2千億円の予備費執行(持続化給付金、緊急小口貸付等)を閣議決定する見込み。同日に衆参の予算委理事懇で政府説明、質疑を行うことに。さらに閉会中審査として19(水)衆厚労委、20(木)参厚労委、26(水)衆内閣委、27(木)参内閣委を開催。
9月第一週に衆参予算委を開くことでは与野党一致していますが、野党は首相出席を要求し、与党は参考人質疑にとどめる姿勢で引き続き協議することになっています。
 こうした報告を受け、午前中に東京を出て、明日の広島の原爆の日のために広島入り。
こうした報告を受け、午前中に東京を出て、明日の広島の原爆の日のために広島入り。
平和公園近くのホテルで、広島市内で開かれたNGO主催の討論会「核兵器廃絶へ日本はいま何をすべきか」を出て、ネット視聴。国連の中満事務次長、ICANのフィン事務局長らに続き与野党国会議員が発言。
日本共産党の志位委員長は、コロナのパンデミックが世界の脆弱性を明らかにしたとして軍事費を削りコロナ対策に回すべきと強調。国際社会に核禁条約の早期発効と核兵器国に過去の誓約を守らせるNPT再検討会議の前進、日本政府に条約参加と黒い雨訴訟の控訴断念を求めました。
 野党合同「河井買収事件実態解明チームヒアリング」に塩
野党合同「河井買収事件実態解明チームヒアリング」に塩
チームが先週、自民党に対して発送した公開質問状につ
自民党本部から河井陣営への1億5千万円の使途につい
さらに、自民党本部からの巨額の資金が「買収目的交付
午前中は国対の会議、昼からは参院議員団の班会議と野党ヒアリング、議員団会議と続きました。団会議では都知事選、都議補選の論戦や反応、野党の共同の広がりなど応援に入った議員から詳しく報告があるとともに、各地での党に迎えいれた経験も交流し、コロナ禍の下で党議員団の論戦や地方議員団の献身的活動を通じて、期待と信頼が高まっていることを実感できました。
さらに、ガンバロウ!